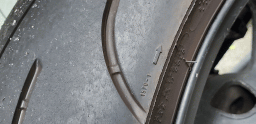 |
| 矢印部分まで、あまリングが残っています |
 様、「あまリング」という言葉をご存じでしょうか。オートバイに乗る方の間で使われる言葉であります。あまリングとはオートバイのタイヤの両端に残る、使われていない部分を指す造語。タイヤの端まで使えていない状態を、輪っか状に見える事から「余る」と「リング」をあわせて「あまリング」と呼ぶようになったとされています。
様、「あまリング」という言葉をご存じでしょうか。オートバイに乗る方の間で使われる言葉であります。あまリングとはオートバイのタイヤの両端に残る、使われていない部分を指す造語。タイヤの端まで使えていない状態を、輪っか状に見える事から「余る」と「リング」をあわせて「あまリング」と呼ぶようになったとされています。
実は、この あまリングを恥ずかしいモノと考えるライダーが、一定数存在するようなのであります。あまリングが残る、=車体を傾けられていない、=ビビっている、=下手くそ、という連想なのだと思いますが、あまリングって本当に恥ずかしいモノなのでしょうか。
あまリングを消す為には、コーナリング時にもっと車体を傾ければ良いようにも思えます。しかし実際にはコーナー手前で早めにブレーキングを済ませ、早い段階で車体を立ててアクセルを開けていったほうが、タイヤにトラクションも掛かりますからスリップダウンしにくくなりますし、結果として速くて安全なのです。摩擦力=摩擦係数×垂直抗力ですからね。同じ路面状況であれば、タイヤにトラクションが掛かるようにしたほうが安全ですし、よりアクセルを開ける事が可能になります。アクセルを開ける事で強烈な旋回力が発生しますから、車体を傾けている時間が短い方が、結果として安全に安定してクイックに曲がれるという訳。
勿論これは中低速コーナーでの話。高速コーナー、つまり半径の大きなコーナーの方が車体を傾けたままでいる時間は長くなります。しかし高速コーナーでタイヤの端まで使う為には、そもそも時速150Kmを超えるような尋常ではないスピードが必要になります。サーキットのようにクローズドで路面ミュー(摩擦係数)の大きな場所であれば可能でしょうが、公道でこのような曲がり方をするなど常軌を逸しているとしか思えません。
サーキットに行かなくても、公道を常軌を逸したスピードで走らなくても、実はもっと簡便にあまリングを消す方法が存在します。8の字走行や小道路転回の練習をすればよいのです。いわゆる教習所的なレッスンをすると、意外なほど簡単にタイヤの端まで使い切る事が出来ます。若い頃、何回か警察主催の安全運転講習(という名のジムカーナ的練習)に参加した事がありますけれども、あまリングなど一切残さずタイヤの端まで使い切る事が出来ましたよ。
警察主催の安全運転講習は、運転免許試験場のコースを利用して行われます。路面の摩擦係数こそ公道と同じですけれども、ここも一種のクローズドコース。こうした特別な機会があるからこそ8の字走行や小道路転回の練習が出来る訳で、こうした練習をその辺の駐車場でやっていたら、すぐに通報されてしまうでしょう。
結局のところ、相当な危険を冒さない限り、普通に公道を走っていて、あまリングを消す事は出来ないのであります。あまリングは恥ずかしいモノでも何でもありません。危険回避の為には、ある意味、正しい臆病さも必須であると申せましょう。
そしてその臆病さは、時に強みともなる。
川崎秋子著「ともぐい」(新潮社)からのお言葉です。ツーリングにおいて、事故なく帰宅する以上に良い走りなど存在しません。完全に法定速度以内に抑えるべきとまでは申しませんが、公道において安全マージンの無い走りはすべきでないと考えるのは自然な事でしょう。私にしても、特に意識している訳ではないのですけれども、常に2ミリほど
あまリングが残っています。私はミシュランのパイロットパワーという銘柄のタイヤを好んで使っておりますが、このタイヤのショルダー部分には回転方向を示す小さな矢印がついていて、ちょうどこの矢印部分までタイヤを使うのが、私にとっての標準的な
あまリングなのでありました〜。
【つづく】
「今週のお言葉」の目次に戻る
「やすなべの目次に戻る」
