 |
|
  |
| 国道439号は、さすが3桁国道って感じ。 大正町と檮原町の境では、既に紅葉が始まっています。 イチョウの黄色い葉が降り積もる路肩でパチリ。 |
 |
| この四国の山々のどこかにスズメ先生が居ます。 でも、範囲が広すぎて捜さらないよ〜。 先生、四国の山の中で、元気で暮らしてね。 |
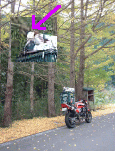 |
| スズメ先生の最後のショット。 ほら、拡大してみると、確かに写ってるでしょ。 |
  |
| 四国カルストにて。スズメ先生がいないので、おいら自ら被写体に。 ここでは冬になる前まで、牛の放牧が行なわれています。 なんか、ハイジが出てきそうな風景。 |
ここで、今までの行動を振り返って見ることにする。あっという間の11日間だったもんね。すごく長かったような気もするし、あっという間だったような気もする。でも、着実においらの中で何かが変わろうとしてるのを感じるんだ。
学校を出て以来13年間勤め続けた会社を辞めて旅に出た。目的だけは「お遍路」としたけれど、それは無目的な一人旅では自分に踏ん切りがつかないような気がしたからであって、いわば目的の為の目的に過ぎなかった。
もともと宗教心のかけらも無い生活をしてきたし、旅に際して信心が湧き上がってきた訳でもない。スタンプラリーとしての「お遍路」を選択し、その方が旅を続けるという観点において自分自身を納得させるのに好都合と判断したのだ。
仕事の都合で仕方が無いとはいえ、10月末のスタートとなったこの旅は、まさに寒さとの戦いである。単車に乗っての移動は物理的に体温を剥奪していくし、身が冷えると精神までもが同時に冷えてくる。
この旅で学んだ最大の事は「家」の有り難さかも知れない。
いわゆる「雨露をしのぐ」という表現があるがこれは言い得て妙である。テントに泊まって実感するのは、雨の恐怖と翌朝の夜露の恐怖だからである。もちろんそれらをしのぐ為にテントは存在するのであるが、「家」と違って夜設営し、朝撤収する際に毎度毎度「家」の有り難さを実感する事になる。
普通の生活においては、家に帰れば風呂が沸いており飯が作ってあり蒲団が敷いてあるのが当たり前と思っていたし、ましてやその事が有り難い等とは一切考えた事が無かった。
話は変わるが、四国には別の空間、「御四国」が存在するという話がある。「四国」とはもちろん徳島高知愛媛香川の4県の集合体であり、日本列島を形成する重要な島の一つである事は周知である。さて問題は「御四国」の方だ。御四国とは遍路巡拝をする中で見えてくる世界であり、それは物理的には「四国」と合致しているが、あたかも異空間のように、ただし歴然と存在する世界であると文献には書いてある。
普段の生活では考えられない「御接待」と呼ばれる自然な施しの風習や、すれ違う見知らぬ人々と交わす挨拶、自らの性格からは想像もつかない平常心の発露等、お遍路をする事によってはじめて見えてくる世界、それらの事象が起こっているフィールドの事を「御四国」と呼ぶ。
だとすれば、今、私は、確実に御四国に居る。
慣れぬ般若心経を唱え、灯明を献上し、線香を立てる。その行為は一見宗教的なだけに見えるかも知れないが、その実、自分自身の内面を旅しているのだと思う。
旅は徳島高知を完了し、明日から愛媛香川に入ってゆく。ただそれは現実の「四国」にシンクロした表現であって、精神的には自分自身の内宇宙を掘り起こしているだけの行為なのかも知れない。
女房に無理行って出させて貰ったこの旅であるが、彼女には感謝してもしきれない。このような経験が、働き盛りの36歳で出来た事は、相当な幸せであると認識する。
芭蕉は奥の細道のなかで「月日は百代の過客にして行き交う人もまた旅人也」と書いているが、遍路巡拝に出ると、その意味が身を持って理解出来る。他人に押し付ける気などさらさらないが、自分の子供にはある年齢になった後、遍路巡拝に出る事を奨めてみようと思う。
| Copyright(C) by Yas/YasZone |